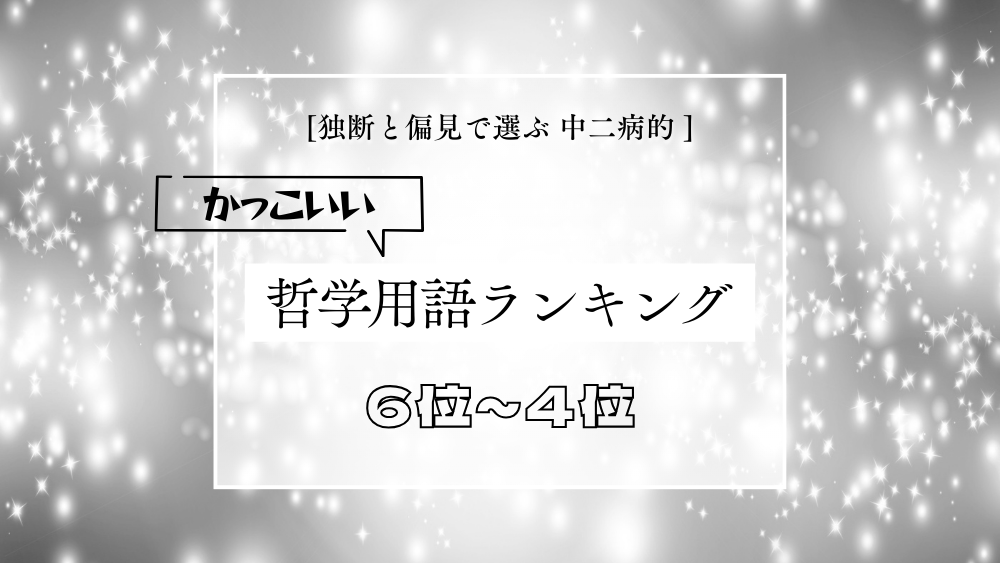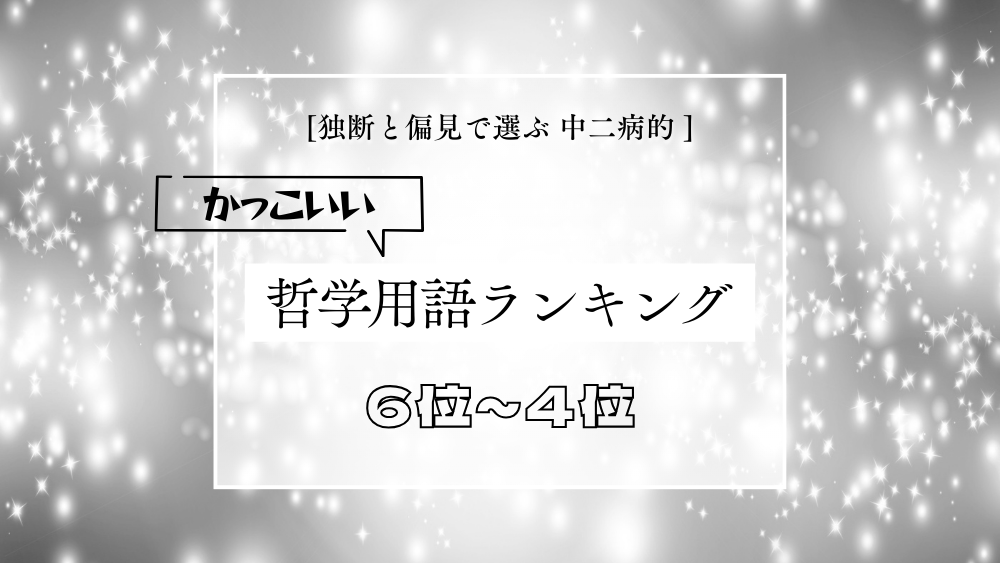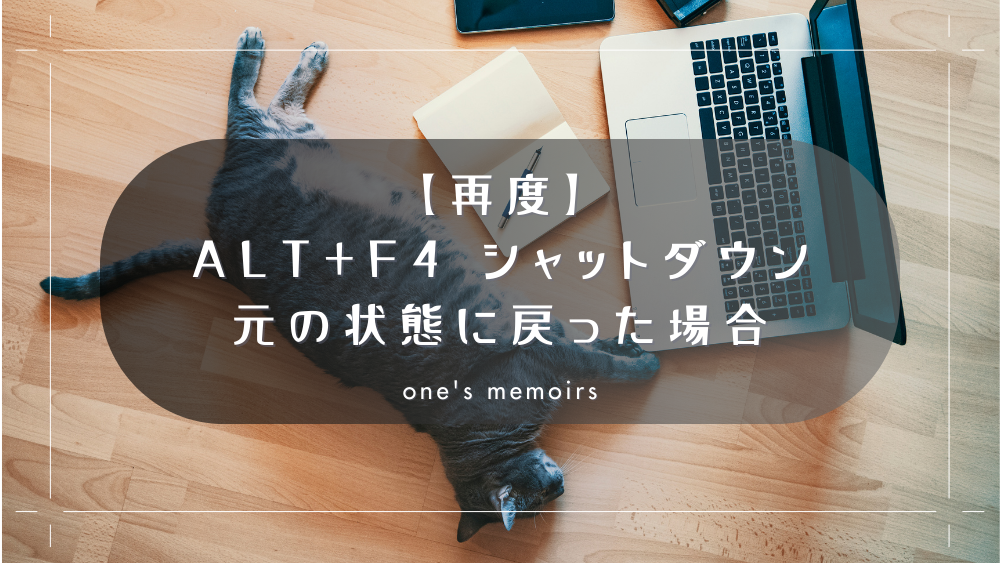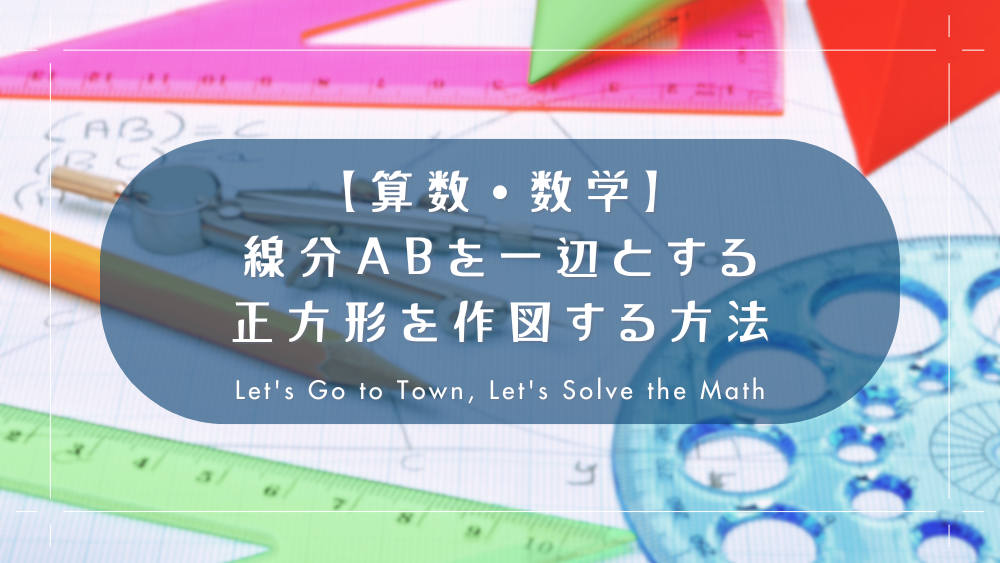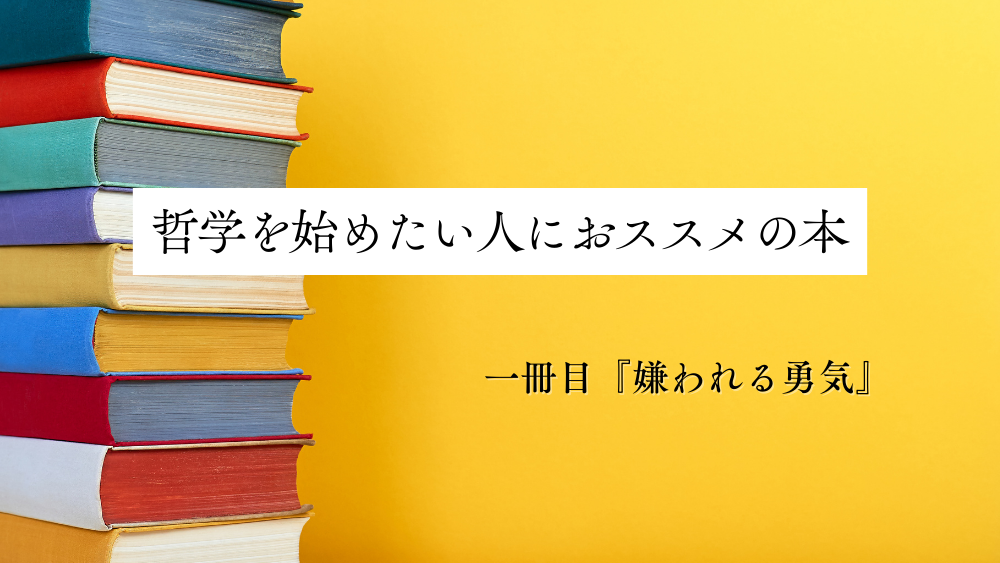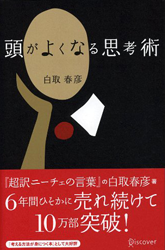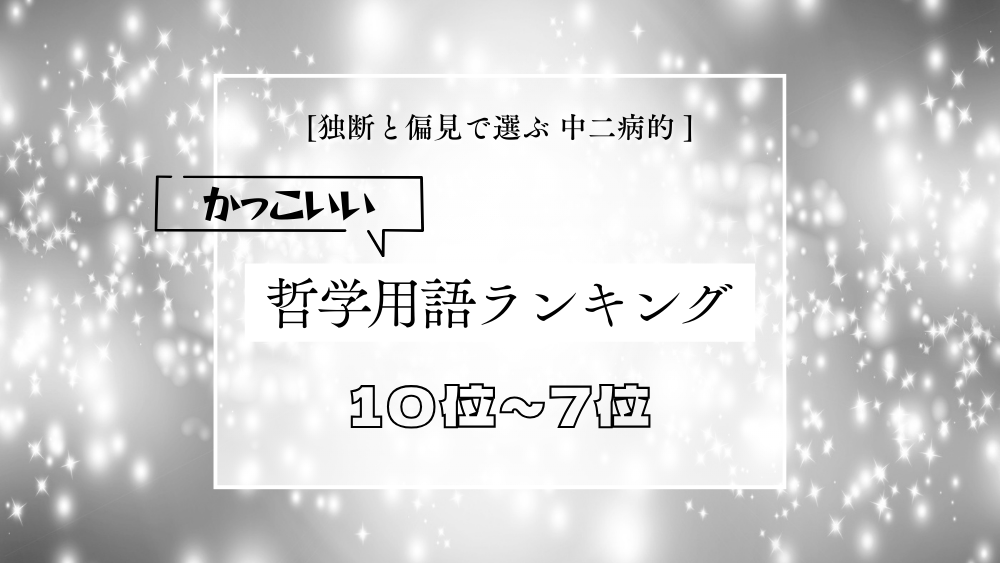
ネットで「中二病っぽい用語ランキング」を見かけて、私も「哲学用語でやってみたい!」と思いました。そこで、完全なる独断と偏見で選んだ「中二病的かっこいい哲学用語ランキング」を作成。
ランキングは三部構成。まずは 第10位から第7位 までをご紹介します!(`・ω・´)キリッ
10位:形而上学(メタフィジカ)
「形而上学(けいじじょうがく)」と書いて「メタフィジカ」と読む…かっこいい(惚れw
この言葉のもとは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの著作『形而上学』にあります。正確には、彼の講義録をまとめた『自然学(フィジカ)』の次に編集・配置されたため、「メタ・タ・フィジカ(=自然学のあとにあるもの)」と呼ばれるようになったのが始まりです。
「形而上」という日本語訳は、「形の上にあるもの」という表現から来ており、そこから「形而上学(メタフィジカ)」は、目に見えない本質や原理 を探究する学問の位置づけとなりました。
では、どんなことを考える学問なのでしょうか。たとえば、
- 「ミツバチの巣はなぜ六角形なのか?」や「ハチミツの成分は何か?」を調べるのは自然学(理科)
- それに対して、「ミツバチを含む世界そのものはなぜ存在しているのか?」や「魂や意識は本当にあるのか?」を問うのが形而上学
つまり、理科や科学では答えられない "世界や人間の根本的ななぞ" に向き合うのが形而上学です。
ほぼ「哲学」と同じ意味で使われることも多く、そこから「では、人はどう生きるのか?」という大きなテーマへつながっていきます。
9位:実存は本質に先立つ(じつぞんはほんしつにさきだつ)
フランスの哲学者サルトルが掲げたスローガン。…用語だけ見ると「何言ってるのか分からない」感じが、めちゃくちゃ中二病ゴコロをくすぐりますw
普通の考え方だと、「ものごとには決まった性質(本質)があって、そのあとに存在がある」と思われがちです。たとえばハサミなら、「紙を切る道具」という本質があって、その本質をもつものがハサミ(存在)として作られる。
でも人間は違う、とサルトルは言います。
人は最初から「こういう存在だ」と決められて生まれてくるのではなく、まず、"存在(実存)" として生まれ、そこからどんな人間になるかを 自分で選び、作っていく のだ、と。
一言でいえば――
人間にはあらかじめ決められた設計図はなく、自分の行動で自分の本質を形づくっていく存在。それが「実存は本質に先立つ」という考え方です。
補足イメージ:
私の感覚では、サルトルの言う実存とは「真っ白な画用紙」のことで、人間はそこに自由に描いていく存在なのだと捉えています。
たとえば「人は助け合うもの」「誰かが悲しめば共に悲しむ」といった傾向や、カントの「ア・プリオリ」のように元からあるような感覚は、紙の大きさや使える色にあたる部分。
でも、どんな絵を描くかは自分の選択に委ねられている。――サルトルが伝えたかったのは、そんな 自由と責任 の感覚ではないかと思っています。
8位:プラグマティズム
「プラグマティズム」とは、19世紀末のアメリカの哲学者パースが提唱した考え方です。
ニーチェやマルクスと同時代に生まれた哲学ですが、ポイントは――「物事の意味や真理は、実際に役に立つかどうかで決まる」というシンプルな姿勢です。
たとえば、氷を考えてみましょう。
- 「氷は水でできている」「氷は熱で溶ける」といった知識も大事ですが、
- プラグマティズム的には、「氷に触ると冷たい」という "体験" こそ意味を持つ、と考えます。
簡単にいうと、私たちの生活の中でどうはたらくか に注目する哲学です。
現代では「ネオ・プラグマティズム」として発展し、「真理は固定されたものではなく、社会の中で常に作り直される」という考え方にも広がっています。
名前の響きがクールで、何かの「必殺技」に使えそうな哲学用語です(※中二病は必殺技が好きw)!
7位:理性の二律背反(アンチノミー)
二つのものが矛盾するという意味の「二律背反(にりつはいはん)」と書いて、「アンチノミー」と読む…しかも、「理性の」と丁寧に修飾語もつけてって、すみません、お腹いっぱいですw
さて、これは哲学者カントが指摘した "理性の限界" を示す有名な問題です。
たとえば宇宙について考えると――
- 「宇宙には始まりがある」と理屈で考えることもできる
- 「いや、始まりはなく無限に続いている」と理屈で考えることもできる
カントが示した「宇宙に関するアンチノミー」
- 宇宙には始まりがある(有限説)
時間を逆戻りすれば、最初の "スタート地点" にたどり着く。
(例:映画のDVDを巻き戻すと最初のシーンで止まるイメージ) - 宇宙は始まりなく続いている(無限説)
時間をどこまでもさかのぼっても終わりはなく、「最初の瞬間」は存在しない。
(例:巻き戻しても巻き戻しても終わらない映画フィルムのイメージ)
両方とも理性(理屈)で考えると筋が通るのに、「始まりがある」と「始まりがない」は両立できない。カントはここから「理性にはどうしても踏み越えられない壁がある」と考えました。
一言でいうと、理性が生み出す "行き止まりのパラドックス" です。
宇宙で例えると、始まりのある・ないは科学で証明できそうですが、カントは有限も無限も 証明したわけではなく、「このように両方のことを考えることができるよね?」と思考の自由度を示した、というわけです。
まとめ
独断と偏見で選ぶ中二病的かっこいい哲学用語ランキング:10位~7位…実は、もっとさらっと1位まで作ろうと思っていたのですが、自分の理解のまとめとして書き出してみたら長くなってしまったので分割しました。個人的メモと思って読み流していただければと思います。(*'ω'*)
【かっこいい哲学用語ランキング:6位~4位】 ↓
【かっこいい哲学用語ランキング:3位~1位】 ↓
良ければ、人生の応援メッセージをランダムで表示するボタンもどうぞ